心リハ指導士の試験ですが、公式の過去問も問題集もありません!!
試験勉強するには日本心臓リハビリテーション学会が出版している、
2022年増補改訂版 指導士資格認定試験準拠 心臓リハビリテーション必携
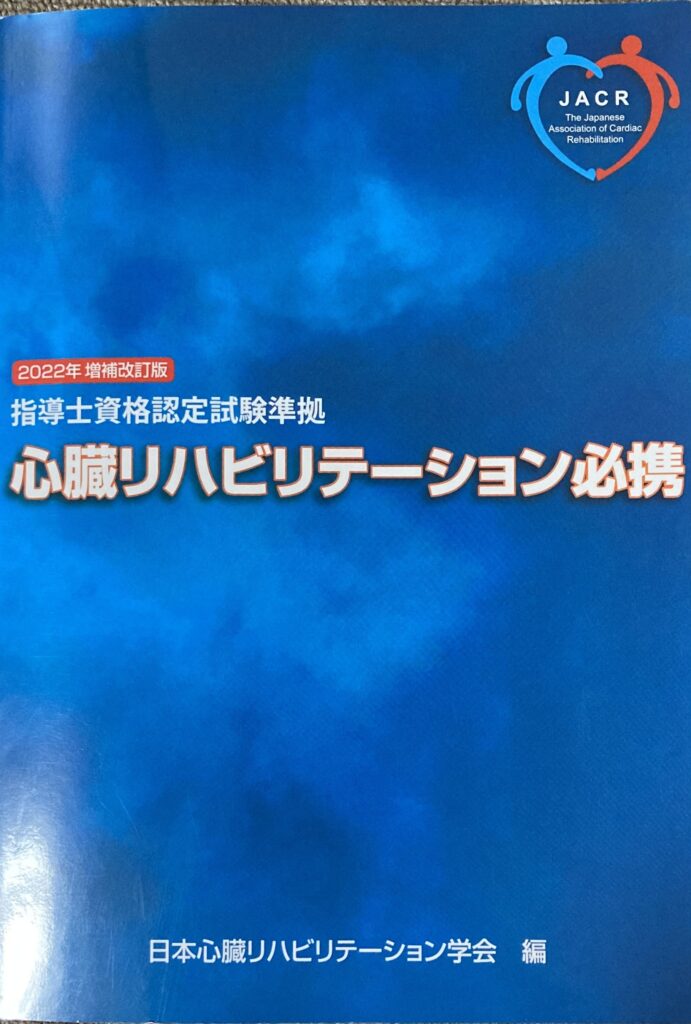
全385ページを読むしかありません!!(さらにガイドラインなどからも出題があります….)
そうなるとあまりにも大変ですし、日々の臨床業務やプライベートを多大に犠牲にしなければいけなくなります…。
そこで、このシリーズは「心リハ指導士への道」と称して私が心リハ指導士の資格を得るために勉強したことをわかりやすくまとめたものとなっています!!
どの投稿から見てもいいようにあえてナンバリングはしていません!!タイトル冒頭の「心リハ指導士への道」を目印に興味のある投稿から読んでいただければと思います!!
それでは今回は「サルコペニア・フレイル」について一緒に勉強していきましょう!!
サルコペニアの定義、診断・疫学
定義
転倒、骨折、身体機能低下、死亡などの負のアウトカムの危険性が高まった進行性かつ全身性の骨格筋疾患!
重要な点は、骨格筋量↓より筋力↓の方が予後悪化と密接に関連していることです!!
診断・疫学
サルコペニアのスクリーニングの重要性は有名であり、自己記入式質問票のSARC-Fや、
骨格筋量の測定が困難な地域でも使用できる指標として、下腿周径とSARC-Fを組み合わせたSARC-Calfによってスクリーニング後、握力or5回立ち座りテストにて確定診断する!!
サルコペニアの有病率は、おおむね6~12%と考えられている。
65歳≦の心疾患患者に対するSARC-Fを用いた調査では、サルコペニアの有病率は男25.9% 女25.0%
フレイルの定義、診断・疫学
定義
加齢に伴う様々な臓器機能変化や予備能力低下によって外的ストレスに対する脆弱性が亢進した状態!
診断・疫学
代表的な診断方法に、「表現型モデル」と「欠損累積モデル」があります。
有名なのは「表現型モデル」で、Friedらによる Cardiovascular Health Study (CHS)があり、日本では日本版CHS(J-CHS基準)によって、予後予測への妥当性が検証されている。
3つ以上該当する場合を「フレイル」、1~2つ該当する場合を「プレフレイル」、いずれも該当しない場合は「健常(ロバスト)」と分類している。
| 項目 | 評価基準 |
| 体重減少↓ | 6ヶ月で、2~3㎏の体重↓ |
| 筋力低下↓ | 握力:男性<26㎏ 女性<18㎏ |
| 疲労感↑ | (ここ2週間で) わけもなく疲れたような感じがする |
| 歩行速度↓ | 通常歩行速度<1.0m/s |
| 身体活動↓ | ①軽い運動・体操をしていますか? ②定期的な運動・スポーツをしています? →上記2つとも「<1回/週」と回答 |
70歳以上の高齢心不全患者(平均81歳)を対象としたFriedらのCHS基準で評価した報告では、フレイルを呈する患者の割合は、76%であり、フレイルを呈する患者はそれ以外の患者と比べて、1年以内の死亡リスクが2.13倍、再入院リスクが1.96倍であったとしています。
サルコペニア・フレイルに対する予防・介入方法
サルコペニア・フレイルに共通する予防・介入法として、栄養療法&運動療法があります!!
栄養療法では、フレイルの中でも身体的フレイルの中核をなすサルコペニアに対して、十分なカロリー摂取、特にタンパク質の摂取が予防・治療に必要となります。
また筋力・筋量などの身体機能の向上には運動療法が必須であり、タンパク質合成を促進するレジスタンストレーニングや有酸素運動を組み合わせて実践することが望まれている。
またフレイルにおいて、運動だけでなく感染予防・社会参加・口腔機能の維持が重要となる。
さらにポリファーマシーとサルコペニア・フレイルとの関連も指摘されています。
*ポリファーマシー:複数の薬剤を服用することで有害事象が生じやすくなっている状態。



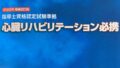
コメント