心リハ指導士の試験ですが、公式の過去問も問題集もありません!!
試験勉強するには日本心臓リハビリテーション学会が出版している、
2022年増補改訂版 指導士資格認定試験準拠 心臓リハビリテーション必携
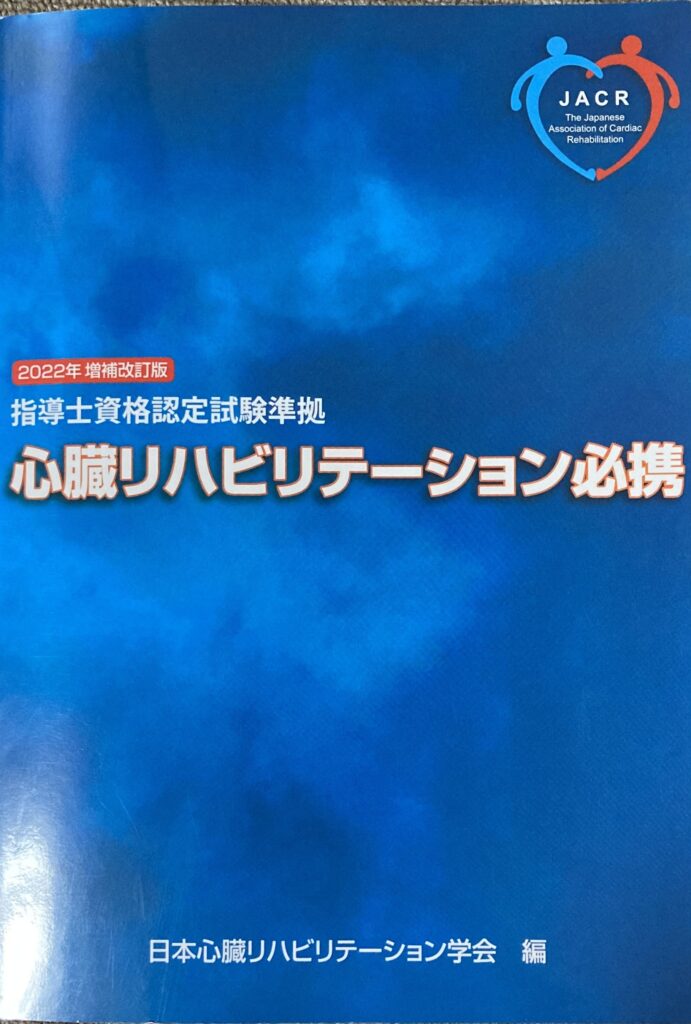
全385ページを読むしかありません!!(さらにガイドラインなどからも出題があります….)
そうなるとあまりにも大変ですし、日々の臨床業務やプライベートを多大に犠牲にしなければいけなくなります…。
そこで、このシリーズは「心リハ指導士への道」と称して私が心リハ指導士の資格を得るために勉強したことをわかりやすくまとめたものとなっています!!
どの投稿から見てもいいようにあえてナンバリングはしていません!!タイトル冒頭の「心リハ指導士への道」を目印に興味のある投稿から読んでいただければと思います!!
それでは今回は「心リハの有効性」について一緒に勉強していきましょう!!
概要
心リハの基本的な利点は以下の通りです。
①運動耐容能の改善
②自覚症状の改善
③脂質代謝の改善
④喫煙率の改善:16~25%の患者は禁煙に成功!
⑤QOLの改善
⑥死亡率の改善:包括的心リハによって3年間の死亡率を25%↓(運動療法のみは15%↓)
⑦安全性
虚血性心疾患における心リハの有効性
虚血性心疾患(≒心筋梗塞)患者に対する運動療法は、3年生存率を50%≦改善し、逆に退院後の死亡の48%が運動療法不参加によるものとまで言われている!!
現在心筋梗塞後の死亡率をここまで改善する薬剤は存在せず、驚異的な二次予防効果となっています!
また安定した狭心症患者に対して、カテーテル治療群と運動療法群で予後を検討した報告では、運動療法群の方が良好な予後を示しています。心事故に関しても運動療法群の方が↓です!
これは、カテーテル治療が局所的な治療にとどまり、新規病変を防げない一方、運動療法は全身治療として有効である側面が表れています!!
心リハによる運動耐容能↑のメカニズムは最大心拍出量&最大動静脈酸素較差↑によるものです!
ここでのポイントは基本は末梢効果(=最大動静脈酸素較差の改善)が主ですが、心筋虚血例では心電図変化などから中枢に対する効果もあると考えられています!
| 冠動脈硬化・冠循環への効果 | 冠危険因子への効果 | 自律神経機能への効果 |
| ・冠動脈硬化↓ ・冠側副路の形成 ・冠動脈内皮機能↑ ・冠微小循環↑ ・血小板機能・血液凝固の抑制 | ・喫煙率↓ ・血清脂質のコントロール ・血圧のコントロール ・血糖のコントロール ・体重↓ | ・副交感神経機能↑ ・交感神経機能↓ |
心不全における心リハの有効性
昔は循環器疾患での治療原則は、「安静」であり、心不全例への運動療法は骨格筋への血流↑、他の主要臓器への血流↓することから禁忌とされてきました。
しかし、近年の報告から心不全例であっても、運動療法により運動耐容能・予後が改善すると言われており、左室駆出率≦40%、最高酸素摂取量が基準値≦80%、BNP 80pg/ml≦(NT-pro-BNP 400pg/ml≦)で医療保険の適応となっています!!
心不全例での運動耐容能↓は左室収縮能の影響ではなく、骨格筋筋肉量↓・代謝異常・血管拡張能↓・呼吸筋の疲労などによる影響が明らかにされてきています!!
| 1)運動耐容能:↑ 2)心臓への効果 ・左室機能:安静時左室駆出率→or軽度↑、運動時心拍出量↑反応↑、左室拡張早期機能↑ ・冠循環:冠動脈内皮機能↑、運動時心筋灌流↑、冠側側副血行路↑ ・左室リモデリング:→(むしろ↓)、BNP↓ 3)末梢効果 ・骨格筋:筋量↑、筋力↑、好気的代謝↑、抗酸化酵素発現↑ ・呼吸筋:↑ ・血管内皮:内皮依存性血管拡張反応↑、一酸化炭素合成酵素発現↑ 4)神経体液性因子 ・自律神経機能:交感神経活性↓、副交感神経活性↑、心拍変動改善↑ ・換気応答:↑、呼吸中枢CO₂感受性↑ ・炎症マーカー:炎症性サイトカイン(TNF-α,IL-6など)↓、CRP↓ 5)QOL:↑ 6)予後:心不全入院↓ |
よって、心不全例でも運動療法は推奨されています!
また運動療法とβ遮断薬併用も問題ないと報告されています!!
心臓手術後における心リハの有効性
| ・運動耐容能↑ ・冠危険因子改善 ・自律神経活性改善(交感神経活性↓・副交感神経活性↑) ・心機能&末梢機能↑ ・グラフト開存率↑ ・QOL↑ ・精神状態↑ ・再入院率↑&医療費↓ |
CABG術後
CABG術後例では、冠危険因子(糖尿病、脂質異常症、高血圧症など)が合併していることが多く、これらの改善のため包括的心リハは必要です!
また完全血行再建例では運動療法は安全に行えますが、不完全血行再建例の場合、虚血が残存しているので運動療法を行う際は十分な注意が必要です!
弁膜症・先天性心疾患術後
弁膜症・先天性心疾患術後例では、病悩期間が虚血性心疾患例より比較的長いです…。
→長期の低運動により骨格筋力・運動耐容能の低下が著しいです…。
ここでポイントは、弁置換術は血行動態を正常化させますが、それだけでは運動耐容能は改善×、血管拡張能・骨格筋などの末梢機能の改善と相まって運動耐容能↑となります!!
また弁膜症・先天性心疾患患者の復職率は、運動耐容能に比例すると言われています!!
血管疾患における心リハの有効性
大血管手術後
期待される効果は、
・術後合併症(感染・肺炎・胸水貯留・せん妄など)の発生率↓
・早期離床&在院日数↓より早期社会復帰が可能
です!!
また、胸部大動脈瘤と腹部大動脈瘤では手術部位が異なるため、それぞれ対応が異なりますが、
胸部=呼吸への影響、腹部=腸管への影響が主となることを押さえておきましょう!
閉塞性動脈硬化症 ASO
動脈硬化は、全身の動脈に生じるため脳・頸動脈、心臓(冠動脈)、腎動脈などの全身の重要臓器と関連する動脈硬化もきたすため様々な合併症が生じていることが多いです…。
閉塞性動脈硬化症 ASO での合併頻度は、虚血性心疾患が 30~50% と最多、次いで脳血管障害 30% となっています。よって運動療法時には合併症の有無に注意が必要です。
下肢虚血に対する治療としては軽症例は低侵襲的治療、重症例は積極的に血行再建を検討します!
特に安静時疼痛例や潰瘍例では運動療法は禁忌で、血行再建を第一とします!!
また間欠性跛行例では、非監視型よりも監視型運動療法の方がより歩行能力↑するとの報告や、ASO患者に対してバイパスのみ、運動療法のみ、バイパス+運動療法の3群の最大歩行時間を比較した報告ではバイパス+運動療法が最も効果が高かったされています!!
運動耐容能↑効果について、運動療法を支持するエビデンスが末梢血管形成術を支持するエビデンスより多いといわれています!(末梢血管形成術がダメてわけではないですよ!!)
その他の病態における心リハの有効性
肺高血圧症
肺動脈性肺高血圧症 PAH や慢性血栓塞栓性肺高血圧症 CTEPH の運動耐容能は↓するが、これは肺循環障害による中枢性機能↓だけでなく、骨格筋の代謝機能↓に基づく末梢性機能↓も大きく関与しています!
デバイス(ペースメーカなど)治療後
近年、徐脈へのペーシング目的のペースメーカ植え込みだけでなく、心室性不整脈への治療(ショック・抗頻拍ペーシング)を目的とした植え込み型除細動器 (ICD)や、心不全治療として両心室の再同期を目的とした両心室ペースメーカ(CRT)など様々なデバイス治療がされてきています!
2011年以降、植え込み型補助人工心臓(LVAD)が保険償還の対象となり、徐々に広がっています。
特に植え込み型LVADは体外式と違って社会復帰が可能な点が大きな相違点です!



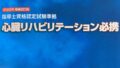
コメント