心リハ指導士の試験ですが、公式の過去問も問題集もありません!!
試験勉強するには日本心臓リハビリテーション学会が出版している、
2022年増補改訂版 指導士資格認定試験準拠 心臓リハビリテーション必携
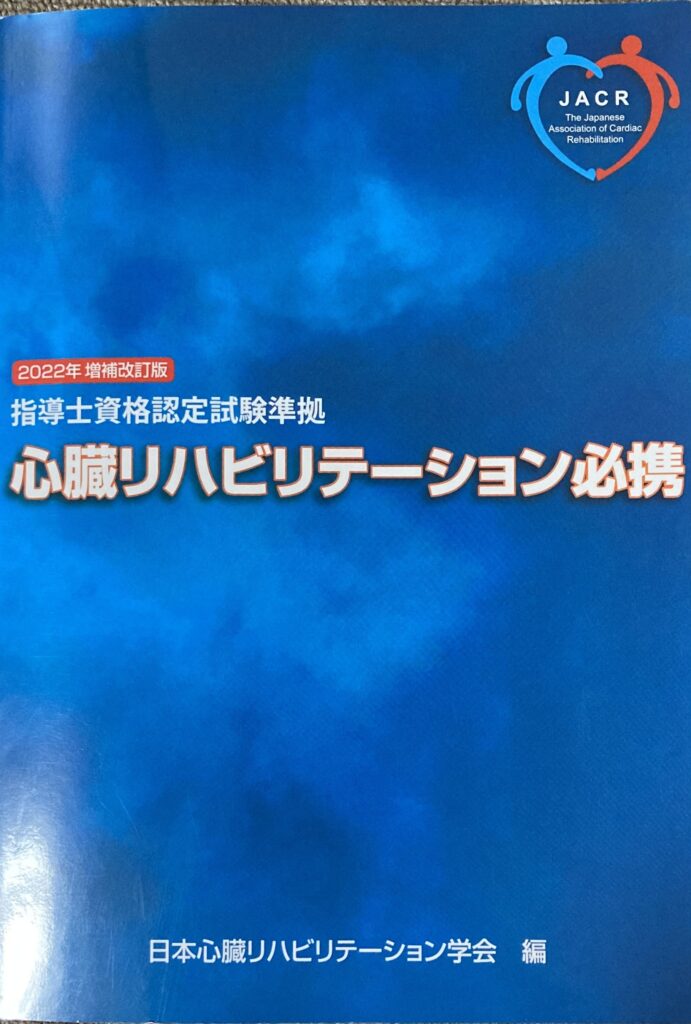
全385ページを読むしかありません!!(さらにガイドラインなどからも出題があります….)
そうなるとあまりにも大変ですし、日々の臨床業務やプライベートを多大に犠牲にしなければいけなくなります…。
そこで、このシリーズは「心リハ指導士への道」と称して私が心リハ指導士の資格を得るために勉強したことをわかりやすくまとめたものとなっています!!
どの投稿から見てもいいようにあえてナンバリングはしていません!!タイトル冒頭の「心リハ指導士への道」を目印に興味のある投稿から読んでいただければと思います!!
それでは今回は「身体機能評価・その他の予後予測指標」について一緒に勉強していきましょう!!
身体機能評価
身体計測
筋力・柔軟性・バランス
包括的下肢機能
予後予測指標
冠危険因子
内因・遺伝性・高尿酸血症を除く主な冠危険因子は、運動療法・心臓リハビリテーションによって改善するとされています。ただし、厳密にはその全てが証明されているわけではないです….笑。
肥満
運動療法単独での減量効果は小さいとしているが、多くの研究で体脂肪率↓を報告しており、肥満が単なる過体重でなく過体脂肪蓄積と考えると十分な改善効果といえます!
ただし、栄養療法+運動療法の減量効果は言うまでもなく、長期的な減量効果の維持には栄養療法+運動療法の方が有効です!!
高血圧
運動療法での降圧効果は多数報告されていますが、運動療法単独での効果かは言及されていないです。ただし、1回の運動療法後にも血圧↓するため、運動療法単独でも降圧効果はあると考えて良さそうです。
また従来、運動療法=有酸素運動であったが、近年レジスタンストレーニングの降圧効果も報告されています。ただし、強度・頻度・方法については統一されていないのが現実です….。
脂質異常症
運動療法単独(有酸素運動)でのLDLコレステロール↓効果は小さいが、HDLコレステロール↑・総コレステロール/HDLコレステロール比↓・中性脂肪↓効果があり、これはフィブラート系薬剤と同等の効果と報告されています!!
要するにLDLコレステロールの粒子サイズを↑し、極悪玉であるsmall dense LDLコレステロールを↓とする。さらには動脈硬化に直接的に関わる酸化LDLコレステロール↓させると報告されています!!
一方、レジスタンストレーニングの効果については、一定の見解は得られていません…。
糖尿病
運動療法単独(有酸素運動)は、インスリン抵抗性↓・インスリン感受性↑・糖代謝↑すると報告されています!!
さらにレジスタンストレーニングの有効性も多く報告されています!!
その他の冠危険因子
炎症
慢性的な炎症→動脈硬化プラークの不安定性に関与していると報告されており、CRP(C反応性蛋白)などの非特異的炎症バイオマーカーは、心血管疾患の予測因子です!!
CRPは、肥満・運動習慣と関連しており、減量によりCRP↓すると健常例において証明されています!! 肥満者や冠動脈疾患例においても同様のことが報告されています!!
ただ、過度な運動は炎症・酸化ストレス↑するため、運動処方には注意が必要です…。
凝固線溶系
運動療法によって、循環血漿量↑・血液粘性↓・血小板凝集能↓と抗血栓効果が得らることが知られています。さらに激しい運動はt-PA↑・PAI-1↓させ線溶系↑させます。
ただし、運動による発汗に対する水分補給が不十分だと血液粘性↑し血栓リスク↑するため、特に高温・多湿下での運動には注意が必要です!!
酸化ストレス
継続的な運動療法により酸化ストレス耐性↑は周知の事実です。
ただし、運動習慣のない人が急激に運動すると酸化ストレス↑するため、適切な運動処方が重要です!
BNP NT-pro-BNP
ともに心不全における過剰な左室負荷に関連し、重症度・予後を反映するバイオマーカーです。
これらは運動療法(有酸素運動)によりカテコラミンと同様に↓する!!
血管内皮機能
心不全例では血管内皮機能に異常があることが報告されています。
血管内皮機能の異常は、血管抵抗↑につながり後負荷&心筋のO₂需要↑するため心不全を悪化させることとなります。また心不全例の内皮機能障害は冠動脈・肺血管・骨格筋にまで及ぶため、運動時の血流増加反応の↓による運動耐容能・身体活動↓など心不全重症度・予後を規定する重要因子です!!
運動療法により血管内皮機能↑・最大O₂摂取量↑し、互いに相関していたと報告されています。
自律神経機能
自律神経機能不全は、①交感神経活動↑②副交感神経活動↓ で表せます。
また自律神経機能不全は、血管内皮機能障害・冠動脈攣縮・左室肥大・心室性不整脈の原因となります。健常例においても高血圧症の新規発生・動脈硬化進行の予測因子であると示唆されています。
運動は、一過性に交感神経活動↑・副交感神経活動↓するが、継続的な運動療法(有酸素運動)によって適度に交感神経活動↓・副交感神経活動↑することが報告されています!!
禁煙
栄養指標
近年、二次性サルコペニア・カヘキシーを念頭においた栄養不良の評価方法・介入方法が検討され始めています。しかしながら現在十分なエビデンスは得られていません…。
CONUT score(下記表)は血清アルブミン値・総リンパ球数・総コレステロール値から栄養状態を評価する方法で最近よく用いられるようになっています。
| 血清アルブミン値 (g/dl) | 3.5≦ | 3.0≦ | 2.5≦ | <2.5 |
| Alb score | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 総リンパ球数 (μL) | 1600≦ | 1200≦ | 800≦ | <800 |
| TLC score | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 総コレステロール値 (mg/dl) | 180≦ | 140≦ | 100≦ | <100 |
| T-cho score | 0 | 1 | 2 | 3 |
| CONUT評価 | 正常 | 軽度障害 | 中等度障害 | 重度障害 |
| CONUT score | 0~1 | 2~4 | 5~8 | 9~12 |
またGNRI(Geriatric Nutritional Risk Index)もアルブミン値を利用した指標として有名で、Ope後患者や透析患者などの生命予後指標として利用されています。
GNRI={14.89×血清アルブミン値}+{4.17×(現体重/理想体重)}
注意点として、血清アルブミン値は循環血漿量による希釈・濃縮の影響、総リンパ球数は感染・侵襲による炎症の影響、総コレステロール値は脂質異常症治療薬などの薬剤の影響があるため、単独での評価は行わず、多角的に評価することが重要です!!



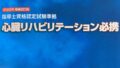
コメント