心リハ指導士の試験ですが、公式の過去問も問題集もありません!!
試験勉強するには日本心臓リハビリテーション学会が出版している、
2022年増補改訂版 指導士資格認定試験準拠 心臓リハビリテーション必携
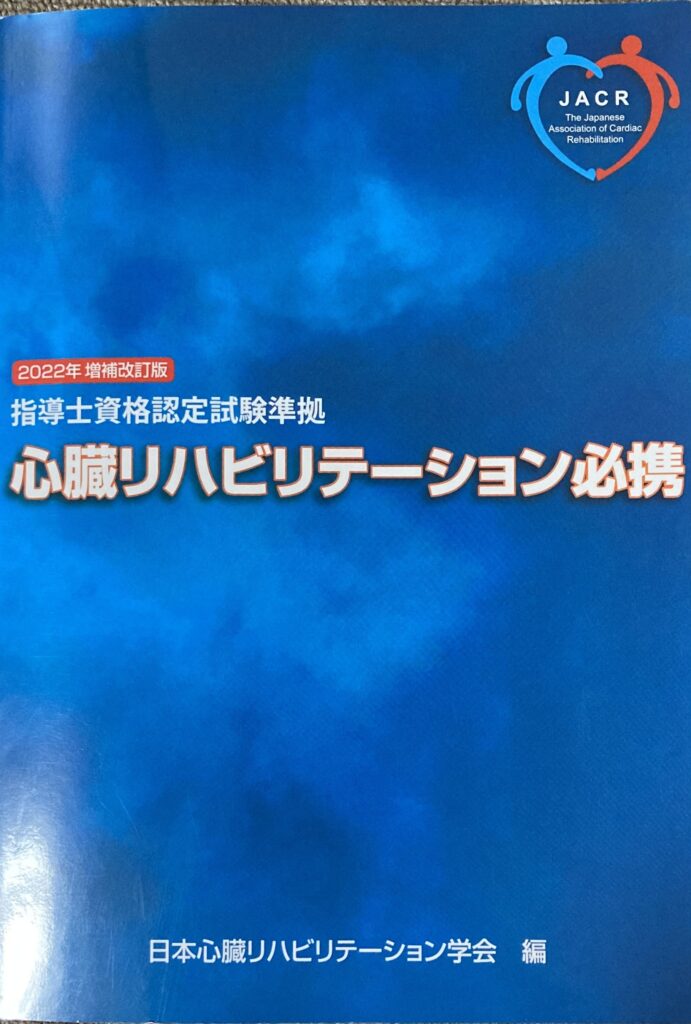
全385ページを読むしかありません!!(さらにガイドラインなどからも出題があります….)
そうなるとあまりにも大変ですし、日々の臨床業務やプライベートを多大に犠牲にしなければいけなくなります…。
そこで、このシリーズは「心リハ指導士への道」と称して私が心リハ指導士の資格を得るために勉強したことをわかりやすくまとめたものとなっています!!
どの投稿から見てもいいようにあえてナンバリングはしていません!!タイトル冒頭の「心リハ指導士への道」を目印に興味のある投稿から読んでいただければと思います!!
それでは今回は「運動生理学」について一緒に勉強していきましょう!!
循環機能
心拍数
成人の安静時心拍数は60~100回/分で、それ以下を徐脈(bradycardia)、以上を頻脈(tachycardia)といいます!
心拍数に対して、橈骨動脈などを触知することで測定する「脈拍数」があり、通常、心拍数=脈拍数ですが、不整脈(特に心房細動)などで生じた心収縮の脈圧は小さいため、脈拍として触知できないことがあり、これにより生じる心拍数と脈拍数との差を「脈拍欠損(pulse deficit)」という。
「脈拍欠損」は、心機能が低下しているほど生じるため、心房細動の患者において心拍数と脈拍数を同時に測定し脈拍欠損の程度を評価することは有用です。
心拍数は、運動強度に応じて直線的に増加しますが、負荷量を漸増させてもそれ以上心拍数が増加しない心拍数を「最大心拍数(maximal HR)」、一方CPXなどで得られる最大値を「最高心拍数(maximum HR)」といいます!!
「最大心拍数」は男女差なく、年齢との間に強い負の相関があり、(220ー年齢)/分の「予測最大心拍数」は有名である。
最大・最高心拍数と安静時心拍数の差を「心拍予備能」といい、Karvonenの式において運動強度の設定法に応用されている。
血圧
収縮期血圧と拡張期血圧の差を「脈圧」、動脈圧波形を時間平均したものを「平均血圧」といいます。
平均血圧は拡張期血圧に脈圧の1/3を足すことで近似できます。(この式の方が有名)
正常値は収縮期血圧130mmHg、拡張期血圧85mmHgとしており、収縮期血圧140mmHg、拡張期血圧90mmHgからは高血圧としている。
冠循環と心筋酸素消費量
冠循環(冠動脈を介する心筋への血液循環システム)の特徴は
- 安静時においても冠動脈血からの心筋の酸素摂取率は70%(他臓器は平均25%)
→心筋の酸素需要増大は冠血流量の増大によって賄われている(効率性には余力がない) - 冠循環は拡張期に血流量が増大する
→低い血圧でしか冠動脈に血流を流せないので狭窄すると虚血になりやすい。
「心筋虚血」とは心筋の酸素需要が心筋への酸素供給量を上回った状態です。
心筋の酸素需要(=心筋の酸素消費量)を規定する因子は
| それなに? | それぞれ50%↑によって心筋の酸素消費量↑は…。 | |
| 心拍数 | 50% | |
| 心筋収縮性 | 心筋のそのものの収縮力 | 45% |
| 心室壁張力(心室容積) | 拡張終期の壁の反発力 =前負荷 | 25% |
| 心室壁張力(心室内圧) | 収縮初期の負荷。収縮期大動脈圧で代用可能 =後負荷 | 50% |
二重積(double productやPRP,RPP)
運動中に測定が簡便な心拍数と心室内圧(=収縮期血圧)の積(心拍数×収縮期血圧)。
運動は最高運動時の二重積を増加、一方最大負荷以下の運動強度の二重積は低下させます。
すなわち、最大負荷以下での心拍数、収縮期血圧の増大を軽減させます!!
またCPXなどの漸増負荷中は二重積は負荷と一緒に漸増するが、ある一点から急峻に変化するようになります。このポイントが嫌気性代謝閾値(AT)と一致します!!
心拍出量
1分間で心臓が排出する血液量であり、身体の大きさを補正するため、これを体表面積で除した「心係数(CI)」といいます!
心拍出量は、心拍数・心筋収縮性・心室容積(前負荷)・心室内圧(後負荷)で規定されるため、心不全患者では心筋収縮性低下を心拍数増大、心室容積の拡大などで代償するため、必ずしも心拍出量が低下するとは限りません!。
心拍出量の測定には「Fickの原理」を使う。
有名なものとしてd、
心拍出量=酸素摂取量/(動脈血酸素含量ー混合静脈血酸素含量)
=酸素摂取量/動静脈酸素含量較差 がある。
動静脈酸素含量較差(A VO₂)
動脈血内と組織を灌流した後の静脈血内の酸素含量較の差である。
動脈血内の酸素含量は変化しないため、末梢(骨格筋)におけ酸素摂取の度合いを示す。
動静脈酸素含量較差の増大は2/3が有酸素運動、1/3が無酸素運動で達成される
心拍出量は最大4~5倍、動静脈血酸素含量較差は最大3倍まで増大するため、酸素摂取量は安静時の最大12~15倍まで増大する。
酸素消費量・摂取量
酸素摂取量は運動強度に応じて直線的に増加するが、負荷量を漸増させてもそれ以上酸素摂取量が増加しない酸素摂取量を「最大酸素摂取量」、一方CPXなどで得られる最大値を「最高酸素摂取量」という。最高酸素摂取量は、負荷中止に至った理由により変動する。
METとは、運動強度を表す単位であり、ある運動の酸素消費量が安静座位の何倍に相当するかを示す。1Mets=3.5ml/分/kgであり、7Mets以上の運動能力があれば日常生活には支障がない。
酸素消費量に対する二酸化炭素生産量の比を「呼吸商 RQ」といい、組織による代謝性のガス交換を反映する。一方、酸素摂取量に対する二酸化炭素排出量を「ガス交換比 R」といい、ガス交換比は組織による代謝性のガス交換のとどまらず、ガス貯蔵の一過性の変化の影響も受ける。
| 呼吸商 RQ | 代謝する物質により変化する。 二酸化炭素生産量/酸素消費量 炭水化物=1.0、タンパク質=0.8、脂質=0.7 |
| ガス交換比 R | 換気量や肺血流量の影響をうける。 二酸化炭素排出量/酸素摂取量 |
換気量
安静時に測定した最大努力下の分時換気量を「最大換気量」という(*心拍数や酸素摂取量と異なり安静時の最大量)。一方、CPXなどで到達する分時換気量を「最高換気量」という。
成人の安静時1回換気量は500ml、通常の吸気からさらに限界まで吸気した際の空気の量を「予備吸気量(2000~3000ml)」という。また通常の呼気からさらに限界まで呼気した際の空気の量を「予備呼気量」という。
要するに、通常からさらに努力性に吸気・呼気した際の空気量をそれぞれ「予備○○量」としている。
肺活量は、1回換気量+予備吸気量+予備呼気量であり、成人で3500~4000mlである。
1回換気量の全てがガス交換に関与するわけではなく、「死腔」と呼ばれるものが存在する。
呼吸系の全体積から肺胞体積を除いた「解剖学的死腔(150ml)」、肺胞には到達したがガス交換に至らなかった「肺胞死腔」からなり、合わせて「生理学的死腔(解剖学的死腔+肺胞死腔)(500ml)」という。
心不全症例では、分時換気量が健常者に対して増大する。
心不全症例では、運動中の毛細血管圧の上昇や、肺胞壁・間質の浮腫などによる肺コンプライアンスの低下により、1回換気量の増大が妨げられるため、その代償として呼吸数を増加させるため、解剖学的死腔が増大する。(同じ分時換気量でも呼吸数が多いと解剖学的死腔の影響をより多くうける。)
さらに運動中の心拍出量の増大が抑制されるため、肺胞において高換気・低灌流のミスマッチをきたし、肺胞死腔が増大する。
よって、心不全症例では生理学的死腔が増大するため、分時換気量が増大、換気・二酸化炭素排出量スロープ(VE vs. VCO₂ slope)が増大する。
代謝
体温調節の仕組みを以下の図に示します。

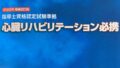
コメント